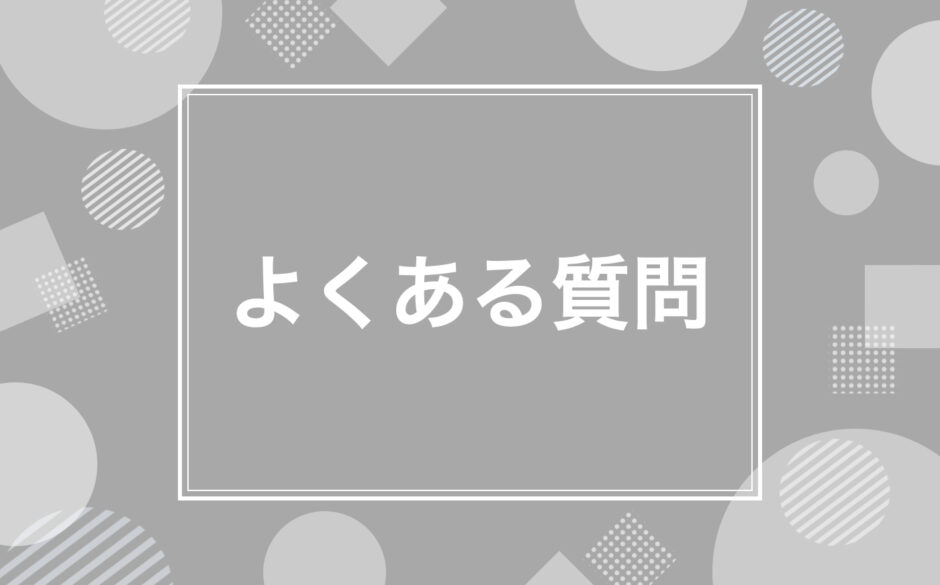A. いくつかの原因があります。以下、1つずつ試してみてください。
- スマートフォンをご利用で音が出ない場合、マナーモードになっている可能性があります。スマートフォン側部にあるマナーモードを解除するボタン(スイッチ等)を押して、マナーモードを解除してください。
- 動画の音量ボタンが「オフ」になっている可能性があります。音量ボタンを押下して、音が出るようにしてください。
- 音量が小さいため、聞こえていない可能性があります。音量をできる限り大きくしてください。
A. はい、できます。スマートフォン(iPhone/Android)、タブレット端末(iPadなど)、パソコン(Windows/Mac)のいずれでも閲覧できます。
A. レッスンは毎週の終わりに、次の1週分がまとめて送られてきます。
A. はい、できます。学習期間が終わった後も、当サイトにアクセスすることは可能です。遡って実施できます。
A. 学習できない日がある場合、以下のように対処しましょう。
- 学習できない日が事前にわかっている場合、その日の分をあらかじめ終わらせてしまいましょう。たとえば、水曜日に学習できない場合、月曜日、あるいは火曜日にその分をやっておけば、遅れることはなくなります。
- 当日になって学習できなくなった場合、翌日、あるいはその次に実施しましょう。たとえば、水曜日に学習できなくなった場合、その分を木曜日、あるいは金曜日に実施すると良いでしょう。
A. 遅れた日が1日程度であれば、当日分と同時並行で行って差し支えありません。遅れた日が2日以上、かつ当日分と同時並行で行うことが時間的に厳しい場合、その遅れた日の分を飛ばしてしまっても構いません。
レッスンを飛ばすことに抵抗を感じる気持ちはわかります。ただ、遅れたままの状態では心理的に焦ってしまうため、本来のペースに戻ることが大事です。
A. 過去に取り組んだ箇所に手応えが感じられず、不安に思う気持ちはわかります。ただ、復習のために止まってしまうよりは、多少わからない箇所があっても、どんどん先に進むことが重要です。
理由は2つあります。1つはペース配分の問題です。たとえ復習のためだとしても、本来のペースから遅れることで、焦りの気持ちが生まれます。すると、復習をしているはずなのに、いつの間にか「全然先に進んでいない。これではダメなのではないか」とますます、焦ってしまうことになりかねません。
もう1つは習得の問題です。英語はあることを習得するのに、その単元で学んだこと以外の知識が必要になることがあります。たとえば、「be動詞がわからない」という時、be動詞について学ぶだけでは、それを習得することはできません。なぜなら、be動詞の後ろには名詞や形容詞が使われる以上、「名詞とは何か」とか「形容詞はどうやって使われるのか」といった、別の知識が必要になるからです。
そうすると、be動詞についてその場の理解が十分でなかったとしても、学習を色々と進めた後、「なるほど、be動詞とはこういう使い方をするんだ」とわかるようになります。
この現象は英文法だけでなく、TOEIC試験対策でも同じです。たとえば、Part5(短文穴埋め問題)でつまづいた箇所があっても、そこで止まることなく、Part6(長文穴埋め問題)やPart7(長文読解問題)など、学習を先に進めることで、英語に対する複合的な経験を得ると、後になって「Part5もよりできるようになった」となります。
もし、復習をするなら、3ヶ月のカリキュラムが終わった後にしましょう。まずはカリキュラムを一通りこなして、学習の全体像がわかった後に復習すると、大いなる気づきに出会えるはずです。
A. もし、プログラムの期間中、すべての学習を2度、3度と繰り返しできれば、それがもっとも効果的なのは、言うまでもありません。
しかし、私たちは皆、日々を忙しく過ごしています。入会当初は学習に時間が取れても、いずれできない日があったり、あるいは遅れてしまうことがあり得ます。
この時、「毎日の学習は2度、3度と繰り返しやらないといけない」と思うと、それが1回でも実現しない瞬間、行き詰まることになります。
それよりは、日々の学習は1度だけでも良いので、毎日続けて最後まで実施するほうが、多くのことを学べます。継続することを第一にすると良いでしょう。
A. 結論的に申し上げると同じです。同じレベルの受験者が受けた時、同じくらいのスコアが出るように設計されています。
ただ、相性の点には差があります。公開テストは紙の問題用紙が配布されるので、IPテストのように操作方法でつまずくことはありません。ただし、会場には他の受験者がいるため、気が散ってしまうこともあります。また、試験時間が約2時間と長いため、集中力の持続が課題になります。
IPテストは通常、約1時間と短縮されているため、比較的集中して試験を受けやすいと言えます。ただし、慣れていないとパソコン画面の操作方法がわからず、時間を浪費することがあるでしょう。また、文字を拡大できないので、視覚的にハードルを感じることもあります。いずれも長所と短所があるので、どちらが良いということはありません。
また、「公開テストで思うようなスコアが出ないから、IPテストに切り替えたら何かが変わるのではないか」といったこともありません。実力を上げてスコアを改善させるほかないのです。
A. 通常、必要ありません。
まず、この記事を書いている2025年6月時点で、『公式問題集』(= 日本で発売されているもの)は12冊出版されています。民間の事業者が出しているTOEIC対策問題集にも優れたものがたくさんあります。
ほとんどの学習者にとって、日本で流通している問題集を正しく行えば、それだけでスコアは上がるでしょう。
A. TOEICを何度も受験し、そのたびに思ったよりスコアが上がらず、あるいは場合によってスコアが下がってしまい、落ち込んでいらっしゃること、大変つらいと思います。
私は過去、70回近くTOEICを受けてきましたから、受けるたびにスコアが右肩上がりで伸びていくということはなく、むしろ毎回のように、上がったり、下がったり、あるいは同じスコアが出て、都度色々と思うことはありました。
なぜ、同じ実力であってもスコアに差が出るかと言うと、一つの原因として「測定誤差」があるからと言われます。
例えば、試験中にわからない問題があっても、偶然正解することはあります。また、正しく解けるはずであっても、不注意による誤答が起こることもあります。体調によるスコアの変化もあるでしょう。
そうすると、たとえ勉強していても、その日の様々な要因で、スコアが上下することがあり得るのです。
古くから「運も実力のうち」と言います。スコアは事実と捉え、目標に向けて、学習を進めていくほかありません。
A. 私は過去、70回近くTOEICを受けてきました。もっとも古くは、今のTOEICの前の前の形式で、その時は今の試験とはかなり異なるものでした。
その後、いわゆる「新TOEICテスト」になってから、私も試験をよく受けるようになりました。新TOEICテストは、私がアメリカに留学に行く際の英語力の証明に必要だったため、一所懸命勉強しました。
そして、2015年に試験問題の大幅改訂があり、今の『TOEIC Listening and Reading Test』の形になりました。その辺りからTOEICにとてもハマってしまい、結果として、現在に至るまで約70回近く試験を受けました。その中で990点満点も取得しました。
『公式 TOEIC Listening and Reading 問題集』(通称、公式問題集)も当然、全部持っています。単に保有するだけでなく、これは少し驚かれるかもしれませんが、Part1からPart7まで、出現する英文をすべて、パソコンの表計算ソフトに入力しています。
このことにより、問題集別に出てくる単語の違い、各パートの出現語彙数の比較、問題タイプの違い、その他出題傾向の違いなどを、詳細に分析しています。
上記の経験、およびデータから私が言えることは、質問者様の求める答えになっておらず恐縮ですが、「TOEICは決して難化していない」ということです。回によって、出てくる単語などに違いこそあるものの、「どんどん難しくなっている」ということはありえません。
そもそも、「TOEICが難化している」という話は、私が本格的に英語を学び始めた15年程前から、よく聞く話でした。でも、もしそれが本当なら、今のTOEICは当時のTOEICに比べて、異次元に難しい試験になっているはずです。
しかし、当時の「公式問題集」などを見ると、問題改訂前なので設問数や一部の問題(= Part7 トリプルパッセージなど)がないといった形式の違いこそあるものの、難易度(= 単語のレベル、リスニングの発話の速さ、長文読解の分量、話題の複雑さ等)はほとんど同じです。同じだから、過去のスコアと今の自分のスコアを比較して、英語力が上がっているとか、下がっていると比較できるのです。
もちろん、実際の試験を受けてみて、以前は単語でそれほど苦戦しなかったのに、今回は知らない単語が多かったということもあるでしょう。ただ、それはその日の試験との相性の問題です。
少し厳しいことをいいますが、ここで「TOEICが難化している」と、むやみに一般化を試みてしまうと、「難しくなっているから仕方ないんだ」とその場で自分を慰める以上のことは得られなくなってしまうのです。
私はかつてから「スコアは事実」と申し上げています。自分にとって必要な学習を、十分に行っていけば、必ずや良い結果は出るでしょう。
A. ダメです。TOEICの規約により、問題用紙に書き込みをすることは認められていません。
ちなみに、英語の聞き取りをしながらメモを取るというのは、私たちが考えるよりも難しいものです。
なぜなら、「メモを日本語で取るのか、あるいは英語で取るのか問題」や、「メモを取っている時、音声が頭に入らず、そこで耳が止まってしまう問題」など、様々な新たな問題が生まれるからです。
そのため、「メモや書き込みは不可」というTOEICの規約は、実は私たち受験者にとって、幸運なことなのかもしれません。
A. 結論的に申し上げると、解く順番を変えても、リーディングを全問解き終えられるようにはなりません。
たとえば、普段はPart5→Part6→Part7と順番どおり解いている学習者がいるとします。Part7の後半数十問を解き終えられず「色塗り」してしまっているため、解答順序をPart7→Part5→Part6に変えるという場合です。
ただ、残念ながら、この作戦はうまく機能しません。なぜなら、これまでPart7を解ききれなかったのが、今度はPart6を全問解き終えられず「色塗り」してしまうからです。
解く順番を変えても、試験時間そのものは変わりません。そのため、リーディングセクションは順番通りに解きつつ、その中で速度を上げていくしかありません。
尚、リーディングセクションの解答速度を上げる具体的な方法は、当講座のMonth3で扱います。
A. 非推奨です。理由は2つあります。
- 現在のTOEICは、Part5が30問、Part6が16問、Part7が54問あります。設問数の少ない Part5 の正答率を上げても、全体の正答率が上がるというわけにはいかないからです。
- Part5 は決して、Part6/Part7 を簡単にしたものではありません。英語の関する幅広い語彙力、およびほとんど全てと言ってよい文法の知識が必要になります。また、語法と呼ばれる、その語彙特有の使い方も問われます。Part5 を極めようと思っても、それは私たちの想像よりもはるかに膨大な学習量が求められるため、挫折してしまう可能性が高まります。
それではどうすればよいかと言うと、結局のところ、Part5からPart7 までを満遍なく学び、総合的なリーディング力をつけていく、という他ありません。
A. 企業によって方針は様々あると思うので、個別の事例についてはなんとも言えません。
ただ、一般論として申し上げると、TOEICは「英語の試験」としての性質のほか、「社員全員への共通の課題」としての重宝されているようです。
たとえば、仮に人事評価に簿記試験が加わると、経理担当者以外にとっては専門外になるため、「なぜ営業(あるいは開発、その他)の私たちが簿記で評価が決まるのか」と反発されるでしょう。
一方、英語であれば、「グローバル化」といった、やや抽象的ではあるものの、もっともらしい大義名分があります。
TOEICを人事評価に加えることで、「共通の課題」にどれだけ取り組んだかを通じて、その人のキャリアに対する真の意欲を見ることができるかもしれません。
本当にキャリアに対して前向きな人なら、その人にとって業務上の意味があるかどうかはさておき、TOEICにちゃんと取り組んで、成果を出すだろうというものです。
もちろん、外資系企業だったり、日系企業であっても業務上、英語を使う場合、その限りではありません。
ただ、英語とはあまり縁がなさそうな企業が、TOEICを評価の一部に加えるのは、上述のような理由があるからではないか… と人事コンサルタントの方に聞いたことがあります。
A.「TOEICスコアが上がると話せるようになるのか論争」、または「TOEICスコアが上がったところで、英語を話せるようにはならないじゃないか論争」は、私が知る限り、15年以上前から存在し、いまだに定期的に出現する話題です。
結論的に申し上げると、TOEIC スコアが上がることと、英語が話せることは、別問題として考える必要があります。なぜなら、TOEIC(L&R Test)はリスニングとリーディングの試験であり、スピーキング能力を測定しているわけではないからです。
仮にいま、”TOEICのみ” を学習している受験者がいるとしましょう。その人がスコアを上げたところで、英語を自動的に話せるようになるかと言えば、おそらくなりません。これが当然なのは、英語はリスニングやリーディングを学習すれば、自動的に話せるようになるものではないからです。
このことは、TOEICが試験としての品質が低いことを意味しません。なぜなら、繰り返しになりますが、TOEICはリスニングとリーディングの試験だからです。スピーキングはリスニングやリーディングの「先」にあるものではないからです。